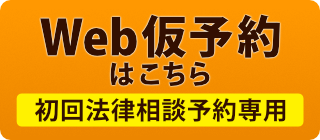2025(令和7)年6月1日施行の刑法改正
犯罪と刑罰を定める現在の刑法は1907(明治40)年に制定されましたが、その後、たびたび一部の条文が改正されています。
このうち、2025(令和7)年6月1日に施行された刑法改正では、118年前の刑法制定以来、初めて刑の種類が変更されました。
これまでの「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止され、新たに「拘禁刑」が導入されました。従来は、刑務作業をする義務がある懲役刑と、刑務作業の義務がない禁錮刑に区別されていましたが、約8割の禁錮刑受刑者が自ら刑務作業を希望するなど懲役刑との区別が曖昧になっていた背景もあり、拘禁刑に一本化されました。
拘禁刑では、受刑者の改善更生や社会復帰を目的として、刑務作業の要否が個別に判断され、特性に応じた更生プログラムが実施されるということです。
この2025(令和7)年6月1日施行の刑法改正は、拘禁刑の新設が話題になりましたが、実はもう一つ重要な改正が行われました。
というよりも、弁護士の実務からすれば、今回の刑の種類の変更は名称が変わった程度にすぎませんが、もう一つの改正である「執行猶予制度」の改正は、実務上とても大きな影響を受けるテーマです。
今回は、この執行猶予制度を巡る改正について説明いたします。
執行猶予制度とは
そもそも執行猶予制度とは何でしょうか。
執行猶予制度とは、有罪判決を受けた際に、直ちに刑務所に収容せず、一定期間その刑の執行を猶予する制度です。
例えば、「被告人を懲役1年に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。」というような判決が言い渡されます。
この制度の目的は、罪を犯した人に社会の中で更生の機会を与え、社会生活を継続させながら立ち直りを支援することにあります。
執行猶予の言い渡しが可能となるのは、3年以下の懲役または禁錮(「拘禁刑」に一本化されたので、以下「拘禁刑」といいます。)または50万円以下の罰金刑に処せられた場合だけで、それを超える重い刑罰を受けた場合は執行を猶予することができず、言い渡された刑が執行されます(いわゆる実刑です)。
執行が猶予される期間は、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間が設定され、この期間中に新たな罪を犯さず執行猶予が取り消されなければ、刑の言い渡しの効力は失われ、刑務所に収容されることはなくなります。
また、執行猶予は、刑の全部でなく、一部のみの執行を猶予することもできます。例えば、「被告人を拘禁刑2年に処する。その刑の一部である拘禁刑1年の執行を3年間猶予する。」という判決が言い渡された場合、1年間は刑務所に服役しますが、残り1年の刑は、3年間の執行猶予となったので刑務所に行く必要はなくなります。
執行猶予は、猶予期間中に新たな罪を犯した場合、基本的に取り消されることになりますが、執行猶予が取り消さると、猶予されていた刑が執行され、刑務所に収容されることになります。
なお、時々勘違いされている方がいますが、執行猶予が付いた場合でも、有罪判決であるため前科となりますのでご注意ください。
執行猶予制度の大きな改正
では、2025(令和7)年6月1日施行の刑法改正において、執行猶予制度の何が変更されたのでしょうか。
一言で言えば、刑事裁判を受ける人に有利となる改正と不利となる改正が行われました。
まず、有利となる改正は、再度の執行猶予を受けられる要件が緩和された点です。
①再度の執行猶予の要件緩和
再度の執行猶予とは、執行猶予期間中に新たな罪を犯した場合でも、情状に特に酌量すべきものがあるときは、もう一度社会内で更生させるチャンスを与えるべく、再び執行猶予を言い渡すことができるという制度です。
改正前の刑法では、再度の執行猶予が認められるためには、1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合で、かつ保護観察中ではないことが要件でした。
しかし,従来のこの厳しい要件では,再度の執行猶予を付けられる事案がほとんどないと言われていて,実際,検察統計によれば,2023(令和5)年に刑の全部の執行猶予を受けた人数は2万7451人であるのに対し,再度の執行猶予が言い渡されたのはわずか136人にとどまっていました。
そこで,改正後の刑法では、2年以下の拘禁刑を言い渡す場合でも再度の執行猶予が可能となり、刑の上限が1年から2年に引き上げられました。すなわち、判決で言い渡される拘禁刑が1年6月や2年の場合でも再度の執行猶予をつけることができるようになりました。
また、改正前は、保護観察付き執行猶予中に罪を犯した場合には実刑にするしかなかったのですが、改正後は、保護観察付き執行猶予中に新たな罪を犯した場合でも、再度の執行猶予が可能となりました。
もっとも、再度の執行猶予で最も重要なポイントである「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という要件は改正刑法でも緩和されることなくそのまま残されたため、実際にどこまで再度の執行猶予の言い渡しが拡大されるかどうかは不透明です。
ちなみに、私自身が担当した刑法改正後に判決が言い渡された執行猶予中に新たな罪を犯した事案では、弁護人として要件が緩和された再度の執行猶予の適用を強く主張したのですが、裁判所は、懲役1年2月(つまり改正刑法により再度の執行猶予をつけることが可能になった刑)を言い渡したにもかかわらず、再度の執行猶予を認めず実刑判決を言い渡しました。再度の執行猶予については,今後の裁判の蓄積が注目されます。
一方で、不利となる改正は、執行猶予期間が公判継続中に満了して判決を迎える事案でも執行猶予を取り消しできるようになった点です。
②執行猶予期間満了後の執行猶予取消制度の導入
改正前の刑法では、執行猶予期間中に更に罪を犯した場合でも、新たな罪の判決の確定までに執行猶予期間が満了すれば、刑の言い渡しの効力は失われる、すなわち、前刑の執行猶予期間中に新たに犯された罪があっても、その新たな罪についての公判が継続している間に執行猶予期間が満了し、判決時には猶予期間が経過している場合には、前刑の執行猶予を取り消されるということはなく、新たな罪の判決で言い渡される刑だけを受ければいいことになっていました。
ところが、改正後の刑法では、執行猶予期間中に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る)について起訴された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間(新たな罪の判決確定までの期間)は刑の言い渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言い渡しが継続しているものとみなされることになり、その結果、新たな罪の判決の確定までに前の罪の執行猶予期間が満了していたとしても、前の罪の刑の執行猶予が取り消されて刑の執行を受けるという可能性が生じることになりました。
とてもわかりにくいですが、要するに、執行猶予中に新たに罪を犯しても、従来は新たな罪に対する判決確定前に執行猶予期間が満了してしまえば執行猶予が取り消されることはなかったのですが、改正後の刑法では、執行猶予中の新たな罪の判決で改めて執行猶予にならない限り、たとえ前の執行猶予期間が満了していたとしても、前の罪の刑の執行猶予が取り消されることになり、結局,前の罪と新たな罪の両方の刑の執行を受けることになりました。この改正は,弁護士でも十分理解していない者もいるかもしれませんので注意が必要です。
いずれにしても刑事事件の手続はとても複雑ですので、もし万が一、警察に逮捕された場合、すぐに当事務所にご相談ください。
弁護士は、必ず、あなたの力になります!