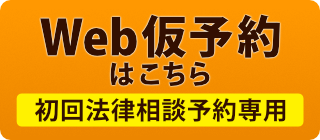「仮差押え」とは何のためにあるのか
貸したお金を返すという金銭消費貸借契約をしたのに借主が返済期限に約束どおりお金を返してくれない時,あるいは売買契約をしたのに買主が支払期限に売買代金を支払ってくれない時など,相手方と一定の交渉をしてもらちがあかない場合には,やむをえず貸金請求や売買代金請求の民事裁判を起こして問題の解決を図ることになります。
ところが,民事裁判で解決する場合,裁判の提訴から裁判の審理を経て勝訴の確定判決を得るまでには一定の時間がかかります。裁判に要する時間については,今から3年前くらいに記事を書きましたので,詳しくは拙稿の2022年12月12日付け弁護士記事「裁判にどれくらいの時間がかかるのか」https://www.f-daiichi.jp/blog/tomo_mouri/4840/をぜひご覧いただきたいのですが,相手方が争った場合には第一審だけでも平均的に1年数か月かかります。
しかも,首尾よく勝訴判決を得られて判決が確定したとしも,相手方がそれに従って素直に支払ってくれない場合には,その後,確定判決を債務名義として相手方の財産に対する強制執行をすることになり,さらに時間を要します。
そうして一定期間をかけて裁判や強制執行の手続をしている間に,もし相手方が自分の保有する財産を処分してしまったら,どうなるでしょうか。
せっかく勝訴判決を得て強制執行をしたとしても,相手方の財産が散逸してしまい,自分の正当な権利を実現することができなくなるおそれがあります。
そこで,そうした事態を避けるために設けられた制度が「仮差押え」です。
すなわち,仮差押えは,民事保全法(以下「法」)という法律で定められているとおり,「民事訴訟の本案の権利の実現を保全するため」(法1条)に設けられたものであり,金銭の支払を目的とする債権(貸金債権や売買代金債権など)を有している者が,民事裁判を起こして判決を待っていたのでは強制執行をすることができなくなるか,または著しく困難となるおそれがあるとき(法20条)に,相手方の財産を仮に差押えて,財産を勝手に処分できないようにする制度です。
なお,「民事訴訟の本案」とは,先ほどの貸金請求や売買代金請求などの民事裁判のことをいいます。
仮差押えの具体的な手続や内容
それでは,仮差押えの具体的な手続や内容について説明します。
まず,仮差押えの申立てをする側を債権者,申立てをされる相手方を債務者といいます。
仮差押えの申立ては,本案の民事裁判を管轄する裁判所か,仮差押えの対象物の所在地を管轄する裁判所に対して行わなければなりません(法12条1項)。
仮差押えをする対象物は,不動産,動産,債権ですが,実務では不動産か債権を仮差押えすることがほとんどです。
仮差押えの申立ては,相手方が保有する財産を処分されてしまわないうちに先手を打つ手続ですので,本案の民事裁判を起こす前に申立てをするのが通常です。ただし,時期的な制約があるわけではなく,本案の民事裁判が確定するまでの間はいつ申立てしても構いません(第一審後の控訴審の途中で申立てることもできます)。
仮差押えの申立てにあたっては,債権者は,被保全権利(債権者の債務者に対する金銭債権の存在)及び保全の必要性(本案の民事裁判の判決を待っていたのでは強制執行をすることができなくなり,または著しい困難を生ずるおそれがあること)を疎明(本案の裁判で要求される厳格な証明よりは簡易なレベルの証明)する必要があります(法13条)。
仮差押え申立ての審理は,債務者に申立てがされたことが知られてしまうと,債務者が急いで財産を処分するおそれがあるため,通常,債務者側には知らせないまま手続が進められます(密行性の原則)。
そして,裁判所が申立てに理由があると認めれば,申立てから数日で仮差押命令が発令されます(迅速性の原則)。
仮差押命令を出すにあたって,裁判所は,申立てをした債権者に担保を立てさせるのが通常です(法14条1項)。これは,仮差押命令の被保全権利が存在しなかったにもかかわらず仮差押命令を受けたために債務者が被る損害を賠償するためのものであり,裁判所や事案の内容によって相当異なるようですが,福岡地裁で実際に私が経験した事件においては,不動産の場合,実勢価格の15%程度,債権の場合,20%程度の担保を要求されました。
一方で,仮差押えは,債権者の被保全権利を保全するためだけの目的であることから,債務者側が原則として被保全権利と同額程度の仮差押解放金を供託すれば,仮差押命令の執行は停止または取り消しされます(法22条)。なお,この場合には,債務者の供託した仮差押解放金が仮差押えの対象物の代わりとなります。
仮差押命令発令後の効力と手続
まず不動産の仮差押えの場合,仮差押命令が発令されると,裁判所書記官の嘱託により,仮差押えの登記がされます(法47条)。
そうすると,仮差押えの登記よりも後に登記された「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」などの権利は,仮差押債権者に対抗することができません。
すなわち,仮差押えの登記がされた不動産の所有者(債務者)が,財産隠しのため不動産を売却した場合,その売却自体が法律上禁止されるわけではないため第三者に所有権移転登記をすることは一応できますが,仮差押えの被保全権利の存在が本案の民事裁判により確定され、債権者が債務名義(確定勝訴判決)を得て,仮差押えから強制執行(本執行)に移行し不動産強制競売を申立てた場合、仮差押登記の後の登記権利者は仮差押債権者に自己の権利を主張することができないのです。
こうして,不動産の仮差押えをした債権者は,不動産の競売による買受代金から自己の金銭債権の回収を図ることができます。
次に債権の仮差押えの場合,仮差押命令が発令されると,第三債務者(仮差押えされた債権についての債務者)に対し,債務者への弁済を禁止する命令が発令されます(法50条)。
仮に、この命令に反して第三債務者が債務者に弁済したとしても、仮差押債権者との関係では弁済がないものとして処理されます。
そして,仮差押えの被保全権利の存在が本案の民事裁判により確定され,債権者が債務名義(確定勝訴判決)を得ると,仮差押えから強制執行(本執行)に移行し債権差押えを申立て,その後,直接第三債務者から取り立てを行い自己の金銭債権の回収を図ることができます。
以上のような仮差押えの手続は,法律の専門的な知識が必要である上,担保金供託や登録免許税納付など面倒な作業も多いので,金銭債権の回収にあたり仮差押えを検討している場合には,お気軽に当事務所にご相談下さい。