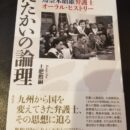『たたかいの論理』(花伝社)は集団訴訟のバイブル!(その1)
大型集団訴訟のレジェンドとして馬奈木昭雄弁護士がいらっしゃいます。先生は、筑豊じん肺訴訟、水俣病訴訟、「よみがえれ!有明訴訟」の弁護団長として闘ってこられた闘士であり当事務所のOBです。
この本は、「馬奈木昭雄弁護士オーラルヒストリー」の副題が示すように、熊本大学大学院講師の土肥勲嗣(どいくんじ)氏が行ったインタビューのテープ起こしが元になっており、馬奈木先生が語りかけているような文体です。今回は水俣病訴訟のパートを取り上げます。
私は、先生が水俣病訴訟に取り組むため当時の諌山博所長の命を受けて水俣に事務所を構えたと思っていましたが(過酷な業務命令だなと思っていました)、実際は自ら希望しての行動であることが書かれていました。
水俣病訴訟は、汚悪水論(おあくすいろん)という戦術で被告企業チッソに勝利をしました。チッソの工場から未処理のまま垂れ流されている廃液自体が水俣病の原因であるとしてチッソの責任を認めさせるもので、廃液中の原因物質の特定に拘泥しないという理屈です。チッソ側は原因物質を様々挙げて攪乱をしてきましたが、それに一々振り回されないで猫実験などから廃液自体の毒性が立証されて画期的勝利を得ました(先生は、原因物質=有機水銀と限定するよりも汚悪水自体の有害性で必要十分とのお考えです)。被告企業がエセ技術論を展開して攪乱するという手法は昔からの常套手段であったようで、これに振り回されないことが肝要なのでしょう。
また、水俣病第3次訴訟熊本地裁判決では、国や県の責任が認められましたが、そこでは水俣病が戦後の国の石油化政策の転換により発生した公害病であるから、国の産業政策を明らかにしたうえでその政策を推進するためにチッソなどに無謀な操業をさせて被害が出ても政策を遂行したことが国の責任の本質だという主張・立証を展開したそうです(立証方法としては、昭和29年当時の水銀の流出量が5トンにも及ぶことの国の資料を証拠として提出)。しかし、今日、このような本質論を他の大型集団訴訟で展開しようとすると裁判所は判決を書くための骨格部分(要件事実と言います)ではないから不要と排斥されてしまう、しかしそれでは肉付けも加えた事件の本質を見ていないではないかという問題点を指摘しています。
国には法律の根拠がなくても国民の安全保護義務がある。人格権の一番の中核をなすのは、もちろん生命身体の安全であり人として尊厳を保ちながら法的権利主体として生活できるということ。この安全保護義務には法律の根拠は不要である。ただし、その義務を果たすための具体的手段としては法律は必要となり、水俣訴訟では水産資源法が魚資源を保護することの背景に魚を摂取する国民の健康を保護法益とすることからこの法律を法源とされました。
裁判所の問題として、別の弁護団が闘った大阪高裁判決を挙げています。大阪高裁では、食品衛生法が本来適用されるはずであることを主張したものの否定されました。同法は商品としての食品に適用されるが、漁師が捕った魚を自分で食べたのであれば商品でないというとして同法の適用を否定しました。プロである漁師が釣った魚はそれ自体が商品であり、それを漁師が食べると商品ではなくなるという酷い屁理屈ですね。
水俣訴訟では、包括一律損害という手法を採ったことでも先駆的です。個別積上げで損害の全部の請求をする方式(完全賠償)だと、損害額の計算をするために大変な労力がかかることと判決によって闘いは終結してしまうが、包括一律請求だと、すべからく共通する損害を慰謝料として請求するのであるから、計算の手間が省力化されるうえに、被害の本質に迫ることが可能になり、裁判後の闘いが継続できる長所を有しているそうです。水俣訴訟では、判決後に将来の医療費一切(鍼灸、温泉療養費に通院交通費まで加えた)と生活費(年金の他に子どもたちの教育費なども含む)を認めさせたそうです。大阪空港訴訟の高裁判決では、被害というのは複雑に絡み合って関連して大きくなることが認められ、(最高裁では引っくり返されたものの)夜8時以降の差止が認められました。このように水俣訴訟での闘いは今日の大型集団訴訟に引き継がれていることが書かれています。